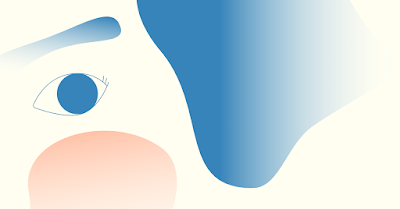桜のささやき
職場の向かいのデスクに座る同僚が、書類の隙間からこちらに視線を送っているのを目尻で感じながら、私はその後ろの窓に広がる桜並木を眺めていた。毎年この時期になると、花は満開に咲き乱れる。 私の名前にはもう一つの候補があった。物心ついた頃、親戚も居合わせた花見の席で、すっかり赤ら顔の父が突然切り出したのを今でも覚えている。 父は初めての娘である私の名前を「さくら」にしたかったのだが、すぐに散ってしまう花の名前では駄目だと祖父母に反対された。代わりに、いな穂のように豊かにみずみずしく育つ意味の込められた「瑞穂」に決まったのだ。 以来酒が進んで調子づくと、父は正月や盆にも「さくら」の話を繰り返した。儚いどころか一年中「さくら」の話に花が咲く父だったが、私が中学に上がるとぱったりと言わなくなった。祖父母が願った通りに、私はいたって健やかに育ち、いつも気力と体力を持て余していた。 ちょうどそのころ、人生で初めて「さくら」さんに出会った。肌は青白いほど透き通っており、小枝のように折れそうな手指が伸びていた。ほっそりとした首すじが二つに結った髪の間から覗くと、同性の私ですら不思議な色気を感じるほどだった。 さくらさんは心身が弱かったけれど、その欠点はいっそう彼女を引き立てた。その度に私は自分を見失っていくのだった。 たくましさゆえに人から粗っぽく扱われた私は、正反対のさくらさんをよく庇っていた。引っ込み思案な彼女が困っていれば話しかけ、体力のない彼女の代わりに重い荷物を持ち、甲斐甲斐しく側にいてやった。そんな私に向かって、小柄な彼女がわずかに上目遣いでこちらを覗き、申し訳無さそうな表情を浮かべると、得体の知れない優越感を抱いた。彼女はいつも「ごめんなさい」と小さく呟いて、脅えるように背を丸めた。 クラス替えを機に、さくらさんはひっそりと私のもとから離れていった。 大人になってからも、二人目、三人目の「さくら」さんは、気づけばひっそりと私の人生から退場していった。 「欠勤が続いていたバイトの佐々木さん、さっき連絡があって辞めますって」 それまで黙っていた同僚が口火を切ると、何者かが私の耳元で小さな声で「ごめんなさい」とささやいた気がした。 「岡野さん、今度はなにをしたんですか」 問いを拒む代わりに、私は視線の先の花々をきっと睨みつけた。私は何も...